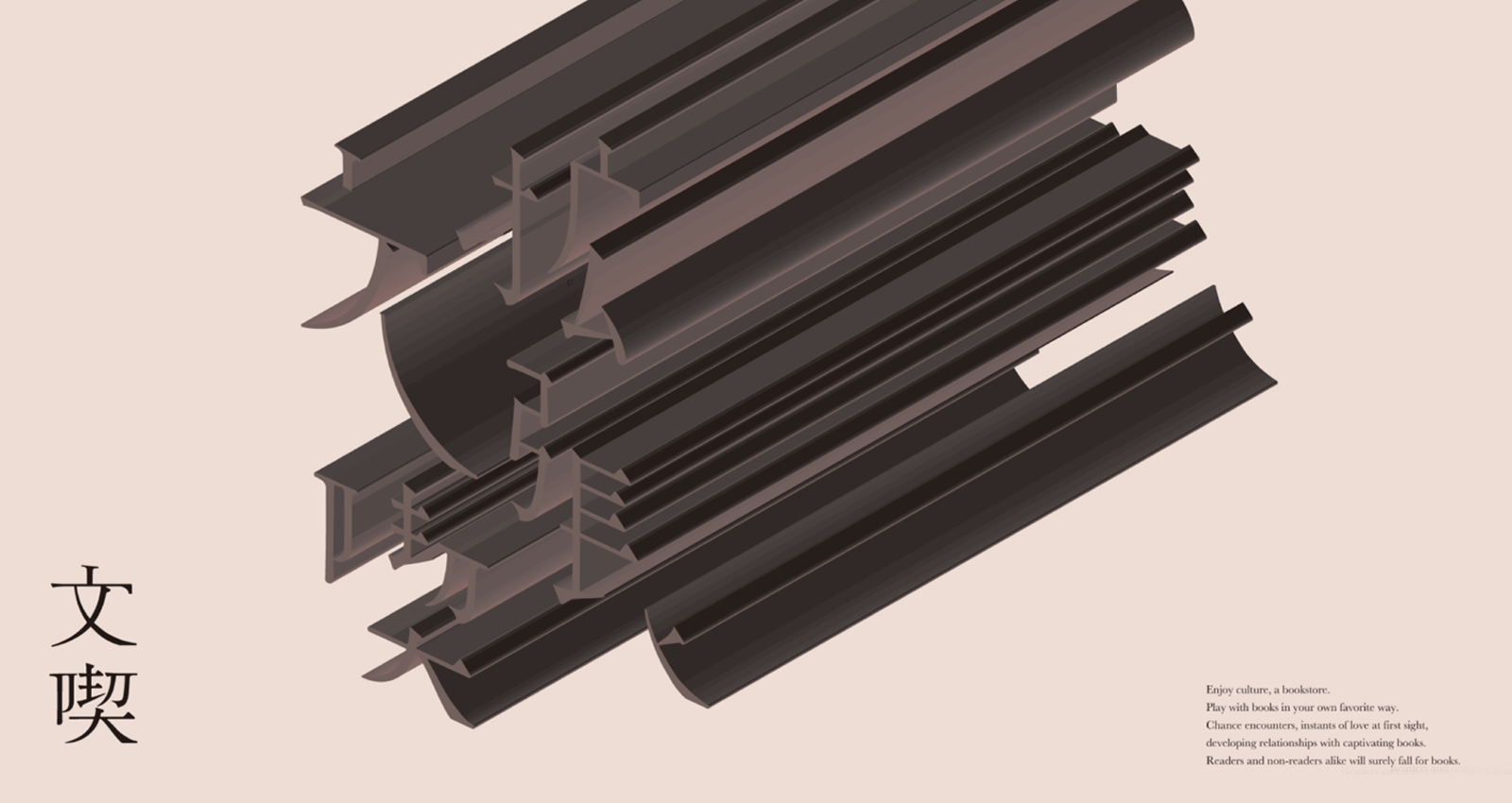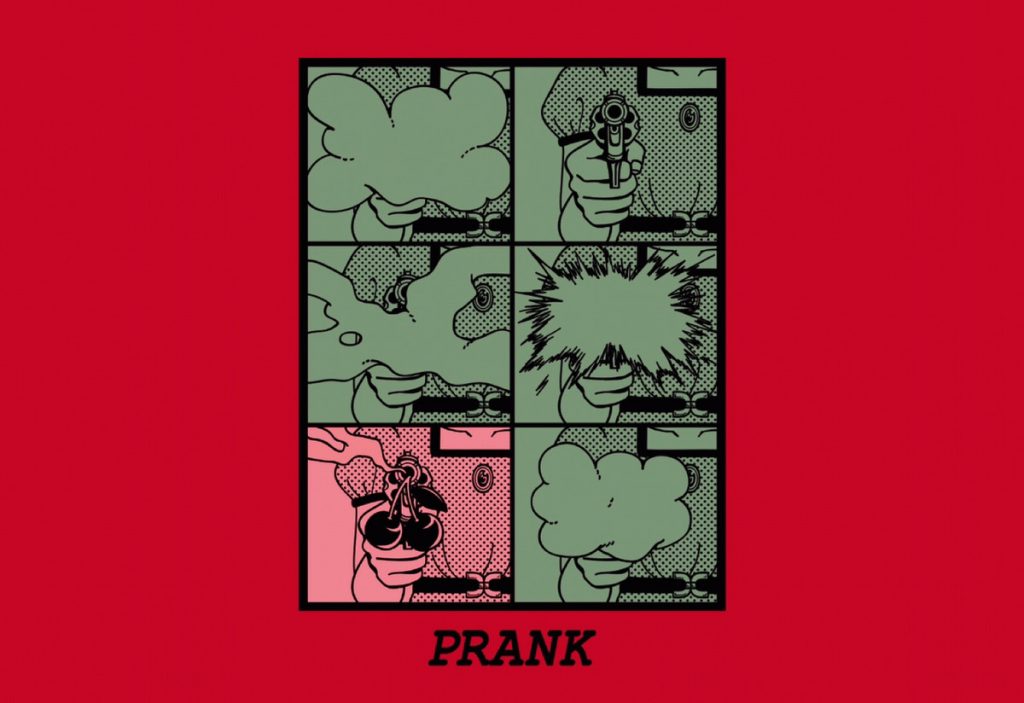
こんにちは。イラストレーターのkisa(@kisa.ne.jp)です。
作品でも言葉でも、なにかを表現してそれを公の場に発信すると、それに対してコメントがくることがあります。
肯定的なコメントをもらえたら活力になりますが、誹謗中傷を受けたらやっぱり心が折れてしまいます。
今回は、言葉の銃弾、「誹謗中傷の捉え方と気にしない方法」についてお話しします。
Contents
誹謗中傷とは何か、なぜ誹謗中傷が起こるのか
SNSやネットニュースのコメント欄など、ネット上での誹謗中傷が問題になっています。
誹謗中傷とは、根拠がないことや悪口を言って、人格を否定したり、人の心を傷つける行為です。
また、そういうことができる理由は「匿名」で顔も晒さなくていいからです。
心理学的にも、匿名だと人は自制心がなくなって乱暴になりやすいといわれています。
なのでコメントと一緒に本名も顔も知られるなら、ひどいことは書けないと思います。
どんな人が書いているのか
匿名だからといって、みんながみんな暴力的にはなりません。
ひどいことを書いてしまう人は、元々性格に攻撃的な部分を持ち合わせているということもあるでしょうが根本は「心が満たされていない人」だと思います。
逆に人生が充実していたら他のことに熱中しているでしょうし、精神的にも余裕があって、そんな気になりません。
仕事やプライベートでストレスが溜まって憂さ晴らししたいとか、嫉妬心や妬みからその人をこきおろしたいとか、中には人の苦しみを喜ぶようなサイコパスもいるでしょう。
誹謗中傷と批判は違う
言論の自由があるので、良いコメントしか書くべきではないとは思いません。
昔、私が描いた絵を「気持ち悪」と言われたことがありますが、ネガティブな言葉なので良い気持ちはしないものの、「この絵はそういう風に感じる人もいるのか」と、一感想として受け止めます。
食べログなどでも、「店内が汚い」「接客態度が悪い」などの否定的な意見もあります。
批判的なコメントは、改善に繋がる場合もあるので、前向きに捉えることが大切です。
でも、「気持ち悪、作者の性格も悪そう」とか「気持ち悪、もう描くのやめろ」は純粋な絵の感想ではなく、人格や表現すること自体を否定しているので誹謗中傷になります。
誹謗中傷されたときの気にしない方法・対処法
スルーする
先ほどにも述べましたが、自身の人生で満たされていない人がする傾向があるので、「幸せを感じてないからそんな乱暴なこと言うのね、可哀想に」と思って無視が一番です。
本人も深く考えずに感情のまま言ったことかもしれないので、有益なことに時間を使っていきましょう。
コメントを見ない
誹謗中傷がSNSによる場合なら距離を置くかいっそ辞めてしまう、ネットニュースや掲示板などなら見ないようにするといったように、目に入れなければ負の感情が生まれることもありません。
身近な人や誹謗中傷相談窓口に相談する
気にしないようにしても、やっぱり気になってなかなか忘れられないとき、自分の中だけで溜め込むのは毒です。
誰かに話すことによってスッキリしたり、具体的な対策なども見つかるかもしれません。
誹謗中傷相談窓口という団体もあり、電話やメール、チャット、SNSでも受け付けているので、気軽に話してみるのも手です。
エスカレートしたら法的に訴える
誹謗中傷は、侮辱罪、名誉毀損罪などの犯罪行為にもなり得ます。
法的措置を取れば、匿名の発信者の情報を突き止めることもできます。
弁護士事務所のアカウントから警告DM・誹謗中傷削除依頼
SNS上で誹謗中傷された場合、弁護士事務所のアカウントから誹謗中傷の削除依頼をお願いすることも可能です。
法的に訴えたくても費用面が心配…というときでも、このサービスなら1件50,000円で対応してくれます。
さいごに
私自身も、ありもしないことや心ないことを言われたことがありますが、そのときは世界が灰色に見えました。
いざその状況になると、なかなか前向きにはなるには時間がかかると思いますが、辛いことを乗り越えられたとき、前よりもメンタルが強くなります。
応援してくれる人や親切にしてくれる人がいるということに目を向けて、ひどいことを言う人がいても負けずに踏ん張りましょう。
また、誹謗中傷する側にならないように、毒舌だとしてもそこに愛があるのかどうかが大切です。(対面だと表情でわかりやすいですが…)
自分のメンタルを穏やかに保てるよう気をつけ、愛のある言葉をかけられる人でいたいものです。